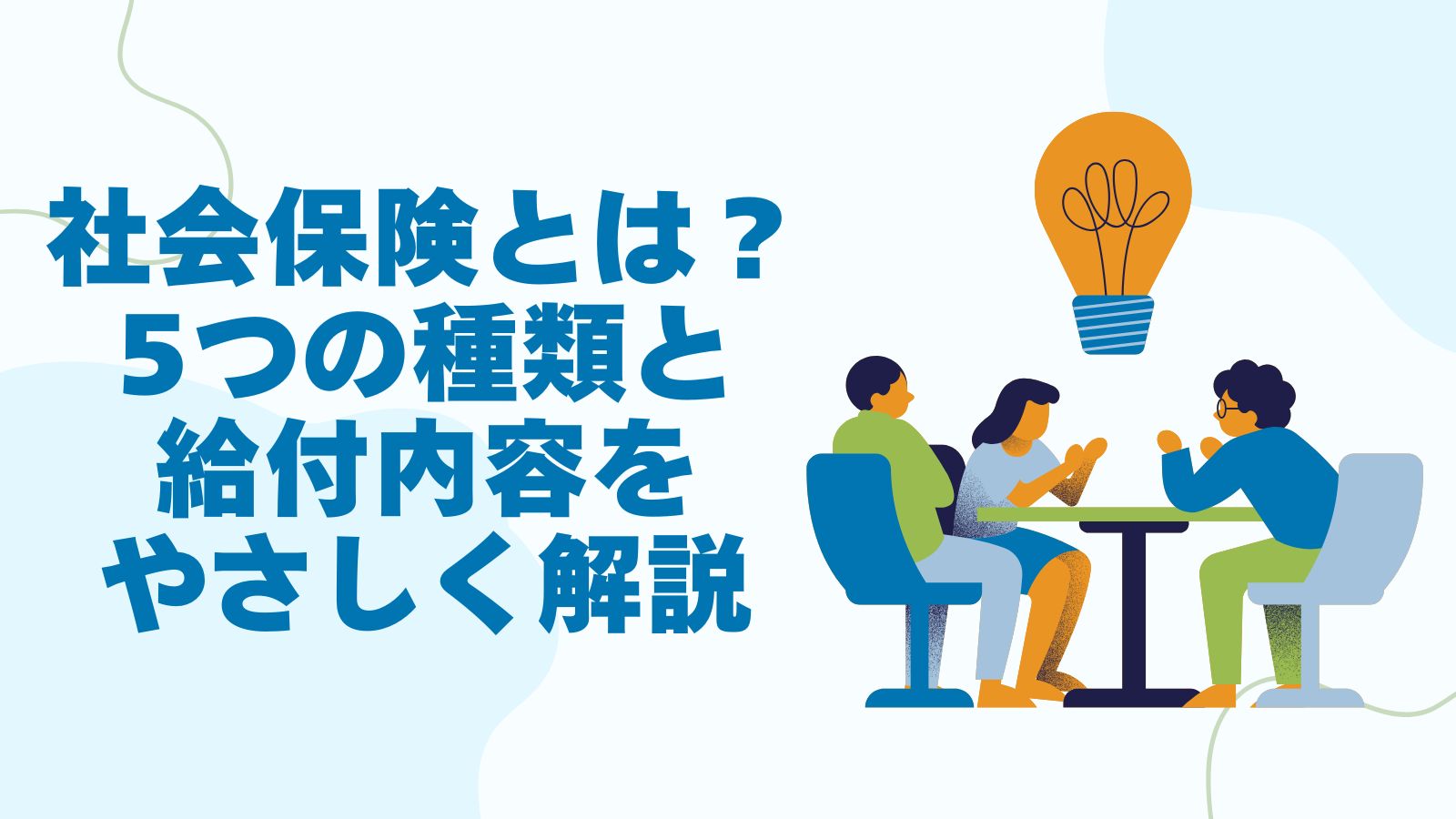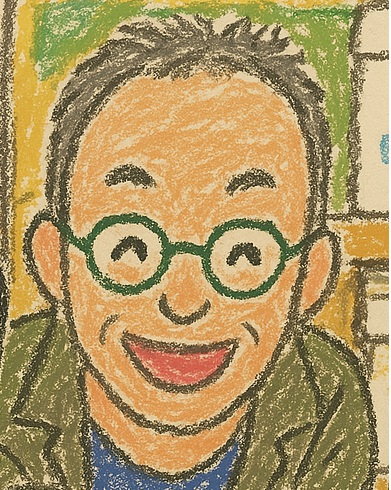「社会保険ってよく聞くけど、実際どんな保障があるの?」「健康保険と年金だけだよね?」
そんな疑問を持っている方も多いのではないでしょうか。
実は社会保険には5つの種類があり、それぞれに私たちの暮らしを支える重要な役割があります。
本記事では、【協会けんぽ加入者】を想定して、社会保険の種類とその保障内容をわかりやすく解説します。
将来の備えや万一のときのために、「自分がどんな保険に守られているのか」を知っておきましょう!
社会保険とは?5つの制度の基本をおさえよう
社会保険とは、「健康保険」「厚生年金保険」「介護保険」「雇用保険」「労災保険」の5つから構成される、日本の公的な保険制度です。
これらは主に会社員や公務員が加入しており、病気やケガ、老後、出産、失業、介護など、人生のさまざまなリスクに備えるための仕組みです。
このうち「健康保険」「介護保険」については、協会けんぽと健康保険組合で制度が異なります。健康保険組合についてはそれぞれ独自の保険料や補償内容となりますので、今回は協会けんぽの制度について説明します。
健康保険(協会けんぽ)の給付内容
健康保険は、保険者である協会けんぽに対し、事業主と被保険者が保険料を負担して運営が行われています。協会けんぽは被保険者とその被扶養者の病気やけが、出産、死亡などの時に必要な医療や現金の支給を行います.
療養の給付(医療費の一部負担で受診できる)
被保険者や被扶養者が病気やけがをした時、一部の負担金を支払うだけで必要な医療を受けることができます。一部の負担金は年齢や収入によって異なります(2割~3割負担)
入院時の食事・生活療養費(入院時の負担軽減)
被保険者や被扶養者が保険医療機関に入院をするときは療養の給付とあわせて食事の給付が受けられます。これを入院時食事療養費といいます。
65歳以上の被保険者や被扶養者が医療療養病床に入院するときは入院時生活療養費が現物で支給されます。
保険外併用療養費(先進医療の一部を保障)
健康保険では認められない治療の内「評価療養」と「選定療養」については、特別な医療を除いた部分に関しては一般の保険診療と同様に扱われ、患者は一部負担金を支払い、残りの額が保険外併用療養費として現物で支給されます。
療養費(海外療養や柔道整復等の払い戻し)
海外で受診した場合など、やむを得ない理由で現物給付(療養の給付)を受けることができないときなどは、かかった医療費を一旦全額支払ったうえで、あとから療養費として払い戻しを受けることができます。
訪問看護療養費(在宅療養者向けの給付)
居宅で療養している方が、かかりつけ医の指示により療養上の世話を受けるときは訪問看護療養費が現物で支給されます。
移送費(緊急移送にかかる費用を補助)
療養の原因である病気やケガにより移動が困難な患者が、緊急やむを得ない場合に医師の指示で移送されたときには移送費が現金給付として支給されます。
高額療養費(医療費の自己負担額を軽減)
医療機関窓口に支払う1か月の自己負担額が所得や年齢によって定められた自己負担限度額を超えたとき、払い戻しの請求をすることで、限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。
傷病手当金(病気で働けないときの生活保障)
被保険者が業務災害以外の病気やケガの療養のため、それまで就いていた仕事に就くことができず給与が受けられないときは、その間の被保険者や家族の生活を保障するため、傷病手当金が支給されます。
出産育児一時金・家族出産育児一時金(出産に関する給付)
被保険者が出産したときは出産育児一時金が、被扶養者が出産したときは家族出産育児一時金が支給されます。
出産手当金(出産に関する給付)
被保険者本人が出産のための会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合は出産手当金が支給されます。
埋葬料・家族埋葬料(万一のときの保障)
被保険者が業務外の事由により死亡したとき、被保険者によって生計を維持されていた家族等がいる場合は、埋葬料が支給されます。埋葬料を請求する家族等がいない場合には、実際に埋葬(葬儀等)を行った者に、埋葬費が支給されます。また、被扶養者となっている家族が亡くなった場合は、被保険者に対して家族埋葬料が支給されます。
厚生年金保険の給付内容
職場を通して加入するのは厚生年金保険です。厚生年金保険の被保険者は、原則として65歳に達するまでは第2号被保険者として国民年金の加入者ともなります。老齢基礎年金(国民年金)に加えて報酬に応じた老齢厚生年金を受け取ることができるほか、障害年金や遺族年金においても国民年金のみの加入者と比較して有利な制度となっています。
老齢基礎年金・老齢厚生年金(老後の生活資金)
老齢基礎年金は、20歳から60歳までの間で10年以上の加入期間がある場合に受け取ることができる年金です。40年(480月)納めた場合に満額の年金額が支給されますが、保険料免除期間や未納期間がある場合は、その月数に応じて減額されます。
老齢厚生年金は、職場を通して厚生年金保険に加入していた被保険者が受け取ることのできる年金です。老齢基礎年金を受け取れることが条件となっています。
障害基礎年金・障害厚生年金(障害を負ったときの保障)
障害基礎年金は、国民年金被保険者期間中に初診日のある傷病で障害の状態になり、障害認定日に1・2級の障害にある人に支給されます。初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに保険料の滞納が被保険者期間の1/3を超えていないことが条件です。
障害厚生年金は、厚生年金保険被保険者期間中に初診日のある傷病で障害の状態になり、障害認定日に1~3級の障害にある人に支給されます。国民年金の障害基礎年金を受けられる保険料納付要件を満たしていることが条件です。
遺族基礎年金・遺族厚生年金(家族を失った遺族への保障)
遺族基礎年金は、国民年金の被保険者や老齢基礎年金の受給権者などが死亡した場合に、生計を維持されていた遺族に支給されます。
遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者や1級または2級の障害厚生年金の受給権者、老齢厚生年金の受給権者などが死亡した場合に、生計を維持されていた遺族に支給されます。
介護保険の給付内容(40歳からの新たな保険)
健康保険の被保険者が40歳になると自動的に介護保険の被保険者となります。介護保険制度は、社会全体で介護を支えることを目的として創られた制度で、介護が必要な状態になっても可能な限り自立した日常生活が送れるよう、介護サービスが提供されます
介護給付(要介護者向けサービス)
日常生活の動作について介護が必要な状態にあるため、施設や在宅でサポートをしてもらうサービスが介護給付です。要介護者に対する給付となります。
予防給付(要支援者の自立支援)
介護が必要な状態になるおそれがある人に対して、予防の観点から実施されるサービスが予防給付です。要支援者に対する給付となります。
雇用保険の給付内容(失業・育児・介護に備える)
労働者が失業したときに、本人やその家族の生活の安定を図るために給付が行われます。また、育児や家族の介護、高齢により継続勤務が難しい場合や失業後の就職促進などについて総合的に支援が行われます。
失業等給付(再就職支援や教育訓練給付)
失業したときに給付される「求職者給付」のほか、再就職の援助を受けるための「就職促進給付」、能力開発の訓練を受けるための「教育訓練給付」、高齢になったり、介護休業をした時のための「雇用継続給付」があります。
育児休業等給付(育児・時短勤務への保障)
育児休業を取得したときに支給される「育児休業給付」に加えて、夫婦ともに14日以上の育児休業を取得した場合に加算される「出生後休業支援給付」、被保険者が2歳未満の子を養育するために時短勤務をした場合に支給される「育児時短就業給付」があります。
労災保険の給付内容(仕事中や通勤中のケガや病気に)
業務上や通勤途上に労働者がケガや傷病を負った場合、労災保険を使っての診療を受けることになリます。
療養(補償)給付
業務上や通勤途上にケガや傷病を負ったときは、労災病院または労災指定病院で診療や投薬などの給付を受けることができます。
休業(補償)給付
療養のため仕事を休んで給与を受けられないときに受けることができる給付です。
傷病(補償)年金
療養開始から1年6月経過後も傷病が治らず、その程度が傷病等級に該当した場合に、休業(補償)給付に代えて支給されます。
障害(補償)給付
傷病が治癒(症状が固定)したときに障害が残り、その程度が傷病等級に該当した場合に支給される給付です。障害等級第1級から第7級に該当するときは年金、第8級から第14級に該当するときは一時金が受けられます。
介護(補償)給付
第2級以上の障害補償年金・障害年金または傷病補償年金・傷病年金受給権者のうち、特定の障害者が介護を要する状態となった場合に支給される給付です。
遺族(補償)給付
労働者の死亡当時その労働者によって生計を維持していた一定の遺族(妻以外は年齢や一定の障害要件あり)がいる場合には年金が支給され、遺族がいない場合には一時金が支給されます。
葬祭料・埋葬給付
労働者が死亡した時、遺族年金・遺族一時金のほかに、葬祭を行った人に対して支給される給付です。
二次健康診断等給付
事業主が実施する定期健康診断で血圧検査、血中脂質検査、血糖検査など一定の項目でいずれも異常の所見があると診断された労働者は、二次健康診断および医師等による特定保健指導が受けられます。
まとめ|社会保険の仕組みを理解して備えよう
日本の社会保険制度は、私たちの生活を幅広く支える重要な制度です。
しかし、多くの給付は「申請しないと受け取れない」ものが多く、知らなければ損をすることもあります。
また、社会保険でカバーされる内容を知ることで、不要な民間保険に入るリスクを減らすことも可能です。
「なんとなく」で済ませず、自分の生活を守るためにも、社会保険の内容をしっかり理解しておきましょう。