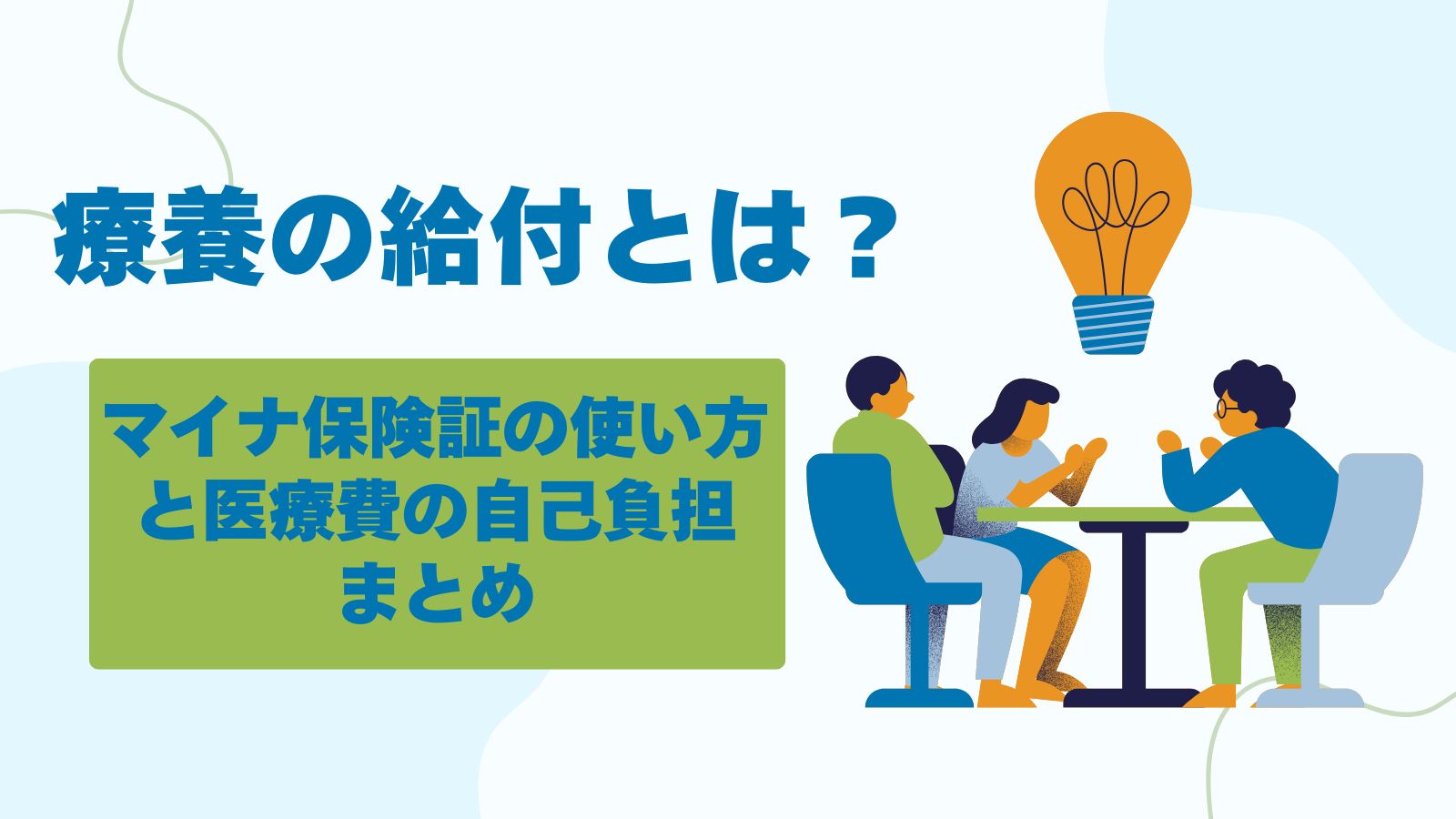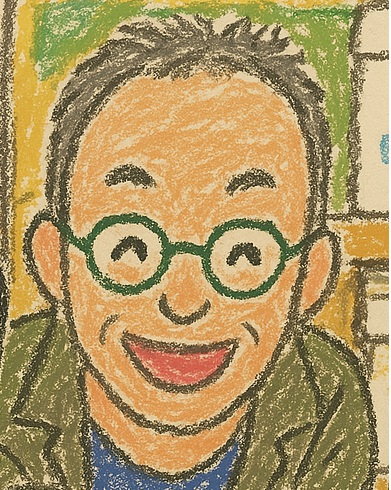健康保険に加入している方が病気やケガをした際、必要な医療を受けられる仕組みが「療養の給付」です。この記事では、マイナ保険証の提示方法や医療費の自己負担割合、対象外となるケースまでわかりやすく解説します。
療養の給付とは?
「療養の給付」とは、健康保険の被保険者(本人)や被扶養者(家族)が、医療機関で診療・投薬・手術・入院などの医療サービスを受ける際に適用される制度です。
自己負担は一部のみで、残りの医療費は健康保険組合などから支払われます。なお、家族(被扶養者)が医療を受けた場合は「家族療養費」として給付されます。
マイナ保険証の提示方法
● 保険医療機関での手続き
療養の給付を受けるには、保険適用の医療機関や薬局で「マイナ保険証」を提示します。これはマイナンバーカードに保険証機能を紐づけたもので、健康保険証として利用できます。
・マイナ保険証を持っている場合 → 「マイナンバーカード」を提示

● マイナ保険証が使えない、持っていない場合
2025年12月2日以降、現在の健康保険証は使用できなくなります。それ以降は以下のいずれかで対応します。
・マイナ保険証に未対応の医療機関 → 「マイナンバーカード」と「資格情報のお知らせ」※1を提示


・マイナ保険証を未取得 → 「資格確認書」※2を提示
・70歳以上75歳未満 → 「高齢受給者証」もあわせて提示

※1 「資格情報のお知らせ」は2024年9月頃に各職場を通して配布されています。もし紛失した場合は、協会けんぽホームページより「健康保険資格情報のお知らせ交付申請書」をダウンロードし、申請してください。「資格情報のお知らせ」の代わりに、マイナポータルアプリより次の手順で「資格情報」を表示し、それを提示することも可能です。
マイナポータルアプリでの「資格情報」表示手順
↓↓↓マイナポータルアプリです

①「マイナポータルにログイン」をクリック

②4桁の暗証番号を入力

③「読み取り開始」をクリックしマイナンバーカードを読み取る

④「マイナポータルをひらく」をクリック(クリックしなくても自動的にひらきます)

⑤「健康保険証」をクリック

⑥資格情報が表示されます

※2 「資格確認書」に関して、私の職場には2025年8月上旬に下記の書類が届きました。マイナ保険証を未取得の方は、順次「資格確認書」を受け取ることができます。


医療費の一部負担金とは?
健康保険を使って診療を受ける際には、医療費の一部を自己負担します。この自己負担額は、年齢や所得によって異なります。
●一部負担金の割合
| 対象者 | 自己負担割合 |
|---|---|
| 義務教育就学前 | 2割 |
| 義務教育就学後〜70歳未満 | 3割 |
| 70歳以上75歳未満(一般) | 2割 |
| 70歳以上75歳未満(現役並み所得者) | 3割 |
●「現役並み所得者」の定義とは?
70歳以上75歳未満の高齢受給者で、以下の条件に該当すると「現役並み所得者」となり、自己負担が3割になります。
・標準報酬月額28万円以上の被保険者とその被扶養者
(被保険者が70歳未満の場合は、その高齢受給者である被扶養者は「現役並み所得者」とはなりません。)
ただし、高齢受給者の被保険者・被扶養者の年収合計額が5,200,000円(高齢受給者である被扶養者がいない場合は3,830,000円)未満であるときは、申請により「一般」に区分されます。
健康保険が使えないケースとは?
以下のようなケースでは、健康保険による「療養の給付」が受けられません。
●労災が適用されるケース
・仕事中のケガ・通勤災害 → 労災保険が優先され、健康保険は使えません。
●病気とみなされないケース
・単なる疲労・美容整形・近視矯正手術など
・正常な妊娠・出産
・定期健康診断・予防接種(原則として)
●故意の事故・不正行為
・わざと事故を起こしたり、虚偽の申告で給付を受けようとした場合も対象外です。
健康保険が使える例外ケースも
・通勤経路を外れた際の事故
・疲労による体調不良で、医師の診断がある場合
・治療を要する美容整形(あざ・ほくろ・シミ等)
・予防接種でも、はしか・百日咳・狂犬病など感染予防目的のもの
・健康診断後の「治療が必要」とされた場合
・妊娠中毒症や異常分娩など医療的介入が必要な妊娠
・母体保護法に基づく人工妊娠中絶
まとめ|療養の給付を正しく理解し、安心して医療を受けよう
「療養の給付」は、私たちが日常的に安心して医療を受けられるための大切な仕組みです。マイナ保険証の活用や自己負担割合の理解、対象外のケースの確認を通じて、無駄な支出を避け、適切な医療を受けられるようにしましょう。