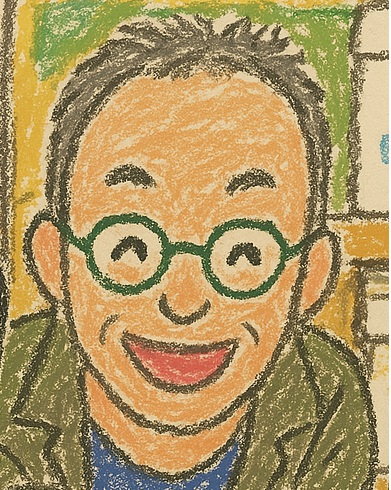医療費が高額になると、家計への影響が心配になりますよね。
でも実は、日本には「高額療養費制度」という、公的な医療費の負担を大幅に軽減できる仕組みがあります。
この制度を理解していれば、民間の医療保険に入らなくても安心できるケースも少なくありません。
この記事では、高額療養費の仕組みや自己負担限度額の具体例、多数該当や世帯合算のルールまで、図を交えてわかりやすく解説します。
高額療養費とは?
医療機関の窓口で支払う自己負担額には、「自己負担限度額」が設けられています。
そのため、1か月の医療費が高額になった場合や、同じ世帯で複数人が治療を受けて合算額が高額になった場合でも、限度額を超えた分が「高額療養費」として払い戻される仕組みがあります。
また、同じ人が何度も高額な医療費を支払った場合も、一定回数を超えると負担が軽減される「多数該当」の制度があります。
自己負担限度額とは?
自己負担限度額(月額)
自己負担限度額は、被保険者や被扶養者の「年齢」や「所得区分」によって月ごとに設定されています。
70歳以上75歳未満の方については、「入院」「通院」によっても限度額が分かれています。
限度額を超えた分は、申請により「高額療養費」として払い戻されます。


【事例】50歳・標準報酬月額400,000円の方の場合
年齢:50歳(70歳未満)
所得区分:「区分ウ(年収約370〜770万円)」に該当
自己負担限度額の計算式:80,100円 +(総医療費-267,000円)×1%
●総医療費が300,000円だった場合
- 総医療費:300,000円
- 本人の3割負担 → 窓口での支払い:90,000円
このときの自己負担限度額は:
80,100円 +(300,000円-267,000円)×1%
= 80,100円 + 330円
= 80,430円(自己負担限度額)
したがって、実際に支払った90,000円と比べると、
90,000円 - 80,430円 = 9,570円
9,570円が「高額療養費」として払い戻されます。
窓口での負担が80,100円(総医療費が267,000円)のとき、自己負担限度額も80,100円となるため、「高額療養費」はありません。
窓口での負担が80,100円(総医療費が267,000円)を超えるとき、「高額療養費」としての払い戻しを受けられます。
多数該当とは?
過去12か月のうち、すでに3回「高額療養費」の支給を受けている場合、4回目からは自己負担限度額がさらに軽減されます。これが「多数該当」の仕組みです。
ただし、70歳以上75歳未満の方が「通院」のみで高額療養費の対象となった月は、多数該当のカウントには含まれません。

自己負担額の計算方法
高額療養費に該当するかどうかを判断するには、次のようなルールに基づいて自己負担額を計算します。
- 計算は「1か月(1日~末日)」単位で行います
- 医療機関ごとに「入院」と「通院」、「医科」と「歯科」に分けて計算します
- 保険外診療(自由診療など)の費用は対象外です
- 入院時の食事代や差額ベッド代などの「特別料金」も対象外です
- 以下の費用は高額療養費の対象となります:
・保険外併用療養費の自己負担額(特別料金を除く)
・療養費の一部負担金相当額
・訪問看護療養費等の基本利用料
世帯で負担が重なったとき(合算高額療養費)
「同一世帯」の定義
たとえ同じ住所に住んでいても、加入している健康保険が異なる場合は「同一世帯」として合算できません。
合算対象となるのは、同じ保険証(記号番号が同一)の家族に限られます。
具体的には、被保険者本人とその被扶養者(配偶者、子など)が対象です。
なお、75歳以上の方は「後期高齢者医療制度」に移行するため、それ以外の家族と合算できません。
一部負担金が21,000円以上のものを合算
1つの月内に、同一世帯内でそれぞれの医療機関で支払った自己負担額が21,000円以上の場合、合算して高額療養費の対象になります。
ただし、年齢により合算対象となる条件が異なります:
- 70歳未満:医療機関ごと、入院・外来、医科・歯科ごとに21,000円以上の自己負担があれば合算対象
- 70歳以上75歳未満:金額に関わらずすべての自己負担が合算対象(ただし、外来には個人限度あり)
【事例】父親と子ども(被扶養者)の合算高額療養費
父親(被保険者):50歳、標準報酬月額400,000円
→ 所得区分「区分ウ(年収約370〜770万円)」
子ども(被扶養者):15歳、中学生
世帯は同一健康保険に加入(記号番号が同じ)
● ある月の医療費の支払い内訳(窓口で実際に支払った金額)
診療を受けた人 | 医療機関 | 診療内容 | 自己負担額 | 合算対象か? |
|---|---|---|---|---|
| 父親 | A病院 | 入院 | 76,000円 | ✅(21,000円以上) |
| 父親 | B歯科 | 外来 | 18,000円 | ❌(21,000円未満) |
| 子ども | C病院 | 外来 | 24,000円 | ✅(21,000円以上) |
● 合算できる金額
- 合算対象になるのは:
父のA病院(76,000円)と子どものC病院(24,000円)
→ 合計:100,000円
● 自己負担限度額の計算(父親の区分ウ)
- 計算式:
80,100円 +(総医療費-267,000円)×1% - 今回の合計自己負担:100,000円 → 総医療費は約 333,333円(3割負担として計算)
- 限度額 =
80,100円 +(333,333円 − 267,000円)×1%
= 80,100円 + 663円 ≒ 80,763円
● 高額療養費として払い戻される金額
- 合算した自己負担:100,000円
- 自己負担限度額:80,763円
- 支給額:100,000円 − 80,763円 = 19,237円
👉 19,237円が高額療養費として払い戻されます
70歳未満と70歳以上がいる世帯の場合の合算例
世帯に70歳未満と70歳以上の人がいる場合、次の手順で自己負担を合算し、高額療養費を計算します。
①70歳以上の外来の自己負担額を個人単位で計算
②70歳以上の入院と外来の自己負担額を合算して世帯単位の限度額を計算
③70歳未満の自己負担額と②でなお残る自己負担額を合算して70歳未満の自己負担限度額を適用
【事例】
お父さん(68歳):A病院 外来 28,000円、B病院 入院 45,000円
お母さん(72歳):C病院 外来 12,000円、D病院 入院 20,000円
(同じ健康保険に加入)
① まず、70歳以上(お母さん)の外来自己負担額を個人限度額と照らし合わせます
(たとえば、一般所得層なら限度額18,000円 → 今回は12,000円なので対象外)
② 次に、お母さんの外来+入院費(合計32,000円)を「70歳以上の世帯限度額(例:57,600円)」と比較
→ 限度額未満なので対象外
③ 次に、お父さんの医療費(合計73,000円)と②のお母さんの分(32,000円)を合算して、70歳未満の自己負担限度額を適用
(例:お父さんの所得区分が「区分ウ(年収370~770万円)」なら限度額は以下)
80,100円+(総医療費−267,000円)×1%
自己負担額105,000円(73,000円+32,000円)→総医療費は350,000円(3割負担として計算)
80,100円+(350,000−267,000)×1%=80,930円
自己負担105,000円 - 限度額80,930円=24,070円が高額療養費として払い戻される
窓口負担を最初から自己負担限度額にするには?
限度額適用認定証とは?
70歳未満の方は、医療費が高額になるとあらかじめ分かっている場合、「限度額適用認定証」を取得することで、窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。
限度額適用認定証は、加入している健康保険組合に申請することで交付されます。
この認定証を医療機関に提示すれば、医療費を一時的に立て替える必要がありません。
限度額適用認定証が不要な場合
「マイナ保険証」を利用できる医療機関では、オンライン資格確認システムにより、自動的に限度額が適用されます。
そのため、限度額適用認定証の申請は不要です。
70歳以上75歳未満の方も、健康保険証と「高齢受給者証」を提示することで、自己負担限度額までの支払いとなります。
まとめ
高額療養費制度は、日本の医療保険制度の中でもとても頼りになる制度です。
民間保険に入る前に、自分や家族の医療費の自己負担限度額や、世帯合算の対象になるかを確認するだけでも、大きな節約につながります。
この記事を参考に、安心して医療を受けられるよう準備しておきましょう。