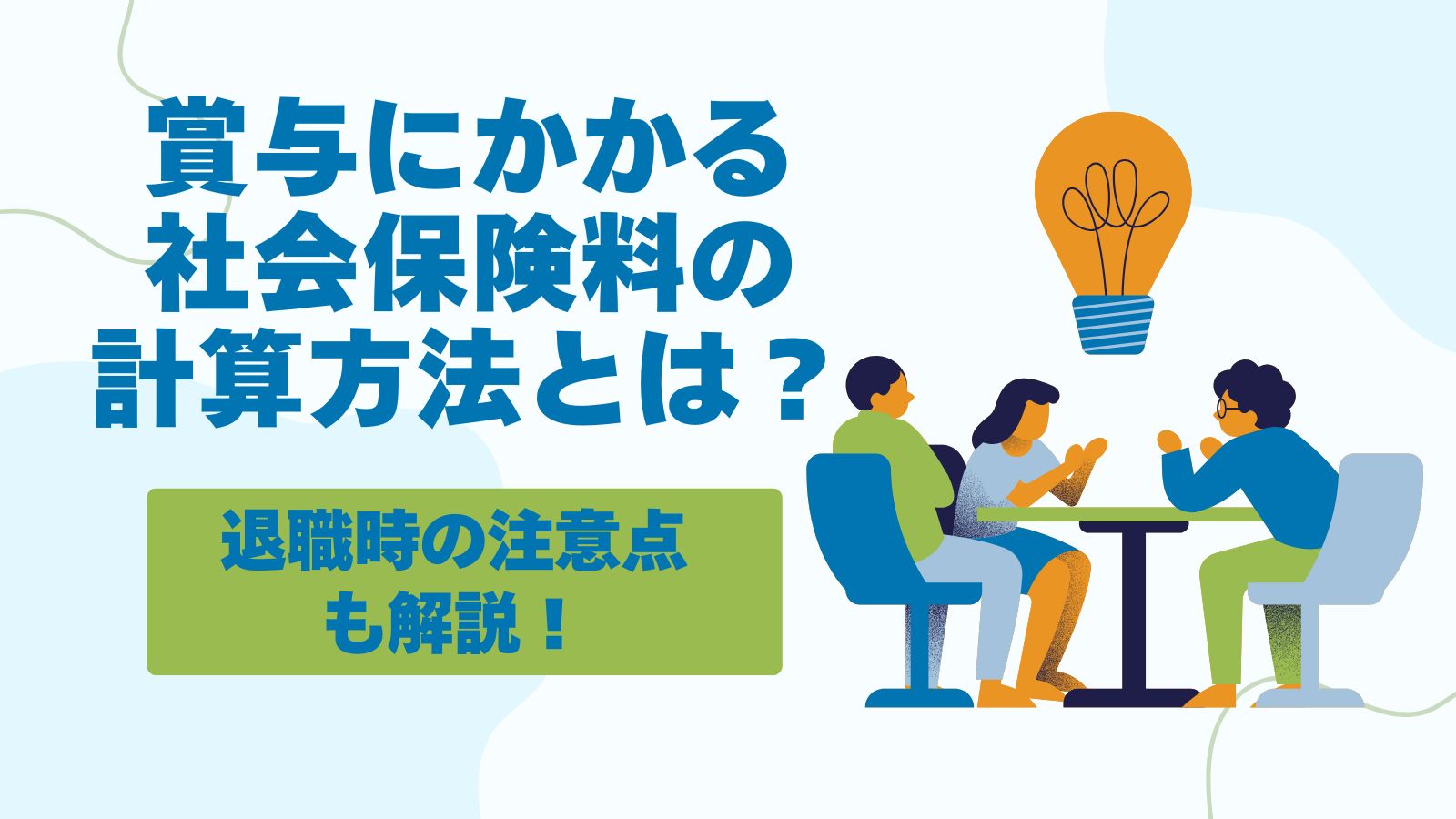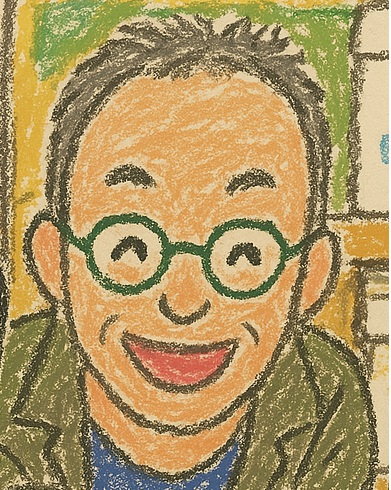賞与が支給されたとき、「社会保険料はいくら引かれるの?」と疑問に思ったことはありませんか?
実は、賞与に対する社会保険料の決まり方は、支給回数やタイミングによって大きく変わります。
この記事では、賞与の社会保険料の計算方法や標準賞与額の決め方、退職タイミングとの関係まで、わかりやすく解説します。
賞与にかかる社会保険料のしくみとは?
賞与に対する社会保険料は、支給回数が年3回以下か、4回以上かによって計算方法が異なります。
- 年3回までの賞与:それぞれの賞与に対して、社会保険料が個別に計算されて控除されます。
- 年4回以上の賞与:年間の賞与総額を12で割り、その金額を月収に加えて「標準報酬月額」が決まります。この場合、賞与支給時に社会保険料は引かれません。
標準賞与額の決め方とは?
賞与時の社会保険料は、「標準賞与額」に基づいて計算されます。
標準賞与額は、賞与額から1,000円未満を切り捨てた金額です。
例:
賞与額が 555,555円 の場合 → 標準賞与額は555,000円
さらに、標準賞与額には上限があります。
- 厚生年金保険:1ヵ月あたり 150万円まで
- 健康保険:年度(4月~翌年3月)で 573万円まで
これを超える部分には、社会保険料はかかりません。
賞与の社会保険料はこう決まる!計算方法を解説
標準賞与額に対して、以下の保険料率をかけ、会社と労働者が折半(半分ずつ負担)します。
| 保険の種類 | 保険料率(概算) | 備考 |
|---|---|---|
| 健康保険料 | 都道府県によって異なる※(94.4~107.8/1000) | |
| 介護保険料(40歳以上) | 15.9/1000 | 対象者のみ |
| 厚生年金保険料 | 183/1000 | 全国一律 |

【計算例:東京都の場合】
- 標準賞与額:555,000円
- 健康保険料:555,000 × 99.1 ÷ 1000 ÷ 2 = 27,500円
- 介護保険料(40歳以上):555,000 × 15.9 ÷ 1000 ÷ 2 = 4,412円
- 厚生年金保険料:555,000 × 183 ÷ 1000 ÷ 2 = 50,782円
※給与天引きする際の端数処理:
被保険者の負担額で0.5円以下は切り捨て、0.5円超は1円に切り上げ(四捨五入ではありません)
賞与支給日と退職日の関係に注意!
意外と見落としがちなのが、「賞与支給日と退職日」の関係です。
これによって、賞与から社会保険料が引かれないケースもあります。
社会保険の資格喪失日は「退職日の翌日」
社会保険の資格は「退職日の翌日」に喪失します。つまり、退職日よりも「資格喪失日」が保険料の有無を左右します。社会保険料は資格喪失日の属する月の前月まで徴収されるので、賞与支給日と資格喪失日が同月の場合は徴収されません。

まとめ|賞与の社会保険は「回数・金額・タイミング」で決まる!
賞与に対する社会保険料のしくみを理解することで、手取り額の予測や退職時の注意点がわかりやすくなります。
以下のポイントを押さえておきましょう。
- 年3回以下の賞与は1回ごとに社会保険料が発生
- 標準賞与額は1,000円未満を切り捨てて決定
- 社会保険料率は都道府県で異なるため、最新の料率表を確認
- 退職と賞与支給日の関係により、保険料が引かれないこともある