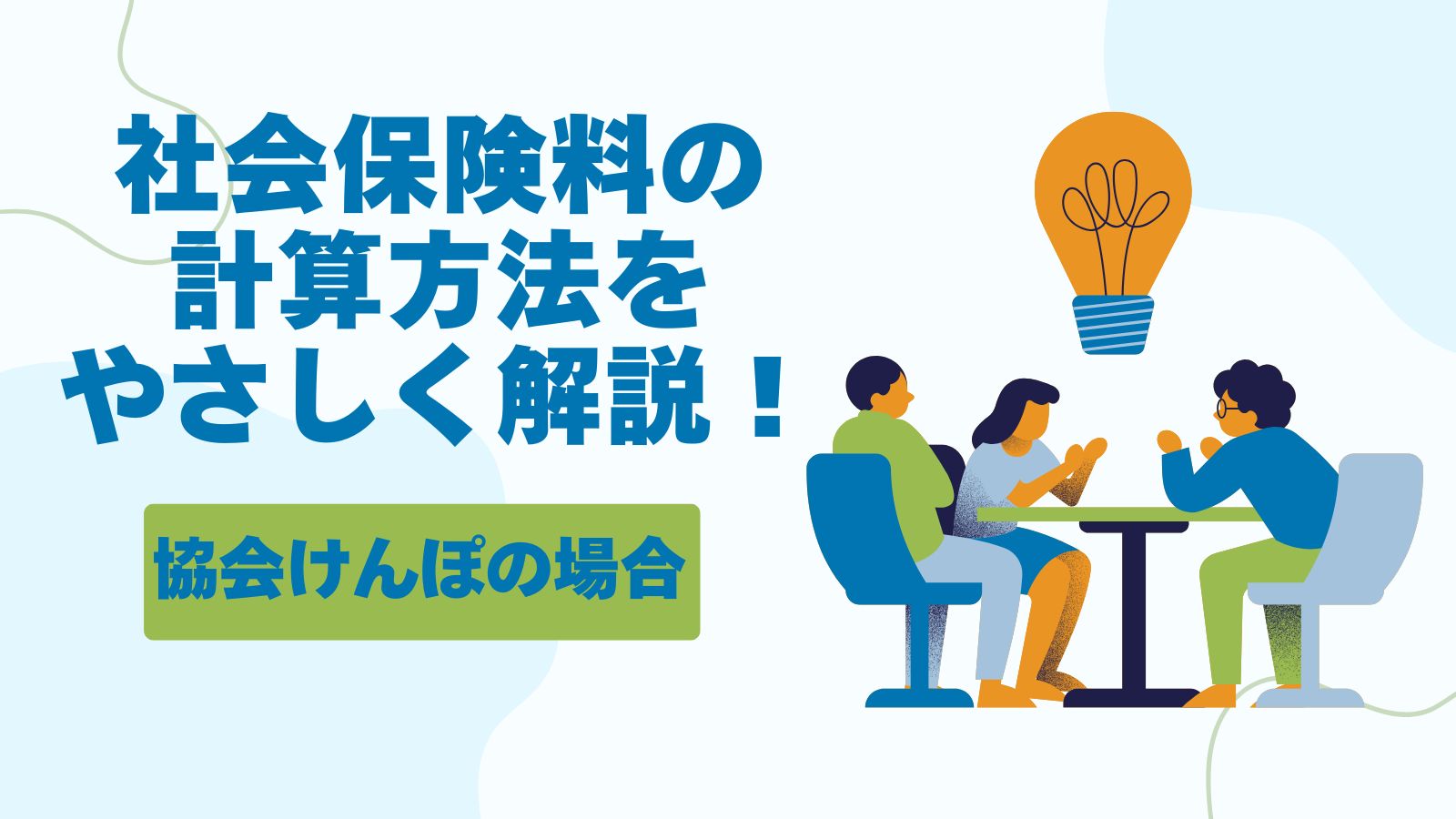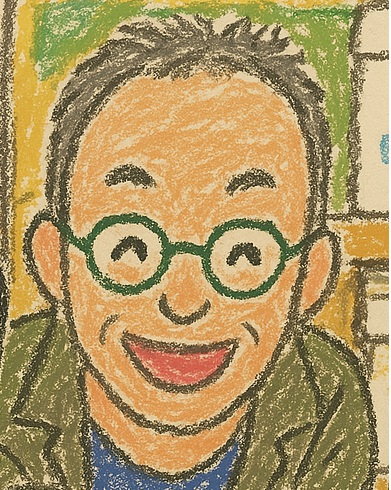社会保険料って高いなぁ…

どうやって計算されているんだろう?

ちょっと引かれすぎなんじゃないの?
そんな疑問を持ったこと、ありませんか?
毎月の給料明細を見るたびに、天引きされる金額にモヤモヤしてしまうことも。でも実は、その社会保険料、計算のしくみがちゃんとあるんです。
今回は、多くの会社員が加入している「協会けんぽ(全国健康保険協会)」における社会保険料の計算方法について、わかりやすく解説します。
社会保険料の中身を知ることで、
✔ 不安がなくなる
✔ 資産管理にも役立つ
✔ ひょっとすると計算間違いにも気づけるかも?
ぜひ最後まで読んで、納得感をもって明細を見られるようになりましょう!
そもそも社会保険ってなに?(社会保険の種類)
社会保険とは、私たちの生活を支えるための公的な保険制度です。大きく分けて以下の5つがあります。
| 保険の種類 | 内容 |
|---|---|
| 健康保険 | 病気・ケガ・出産時の医療費などをサポート |
| 厚生年金保険 | 将来の年金・障害や遺族の年金など |
| 介護保険 | 40歳以上の方が負担、介護サービスに利用 |
| 雇用保険 | 失業時の給付や育児休業給付など |
| 労災保険 | 仕事中のケガ・病気に対する保障 |

このうち、狭義の「社会保険」と呼ばれるのは「健康保険」「厚生年金保険」「介護保険」の3つ。
「雇用保険」「労災保険」は「労働保険」に分類されます。
社会保険料の計算方法はこう決まる!
社会保険料の多くは、給与や賞与(ボーナス)などをベースに計算されます。
保険ごとに計算方法が異なり、「いつ決まるのか」や「どう変更されるのか」も大切なポイントです。
ここからは、計算のタイミングごとに順を追って説明していきます。
健康保険・厚生年金保険・介護保険の保険料はこう決まる!
健康保険・厚生年金保険・介護保険の保険料が決まるタイミングは次の4つになります。
- 資格取得時決定(入社時など)
- 定時決定
- 随時改定
- 産前産後休業終了時改定、育児休業等終了時改定
資格取得時決定(入社時など)
入社時などに決定する社会保険料は、基本給+各種手当の合計(報酬月額)がベースになります。

※自治体によって健康保険料率が異なるため、保険料額表も自治体によって異なります。
実際の保険料額表は、こちらをご覧ください。
▼計算例
Aさん(45歳・東京都勤務)
- 基本給:350,000円
- 通勤手当:20,000円
- 家族手当:15,000円
→ 合計:385,000円(報酬月額)
この報酬月額を東京都の保険料額表に当てはめると、

標準報酬月額380,000円 (健康保険 第26級、厚生年金保険 第23級)なので、
健康保険料18,829円・介護保険料3,021円(21,850円−18,829円)・厚生年金保険料34,770円となります。
※決定月が1月〜5月の場合はこの金額が8月まで適用され、6月〜12月の場合は翌年の8月まで適用されます。
定時決定(毎年7月)
資格取得時(入社時)に決定した標準報酬月額は給与の見込み額により決定されたものですが、その後、昇給や残業手当の増減等により月々の給与額は変動する可能性があります。こういった給与の実態を標準報酬月額に反映させるため、年に1回標準報酬月額の見直しが実施されます。これを「定時決定」といい、社会保険料は4月、5月、6月の基本給+各種手当の合計を3で割った額がベースになります。

※保険料額表は、こちらをご覧ください。(資格取得時決定の時と同じ表です)
定時決定の詳細については以下の記事で紹介していますので、参考にしてみてください。
▼計算例
Aさん(46歳・東京都勤務)
現在
- 標準報酬月額:380,000円(健康保険 第26級、厚生年金保険 第23級)
- 健康保険料18,829円・介護保険料3,021円・厚生年金保険料34,770円
4月に昇給
- 基本給:365,000円
- 通勤手当:20,000円
- 家族手当:15,000円
→ 4月:400,000円、5月:400,000円、6月:400,000円
→ 3ヶ月の平均:400,000円(報酬月額)
この場合の社会保険料は、この額を東京都の保険料額表に当てはめると、

標準報酬月額410,000円 (健康保険 第27級、厚生年金保険 第24級)なので、
健康保険料20,315円・介護保険料3,260円(23,575円−20,315円)・厚生年金保険料37,515円となり、この金額が9月から翌年の8月まで適用されます。
随時改定(大きな昇給・残業増など)
被保険者の受ける報酬に大幅な変動(昇給や降給など)があった際、実際に受ける報酬と標準報酬月額との間に差が生まれてしまいます。実際に受ける報酬と標準報酬月額との隔たりを解消するために実施されるのが「随時改定」です。社会保険料は変動月から3ヶ月間の基本給+各種手当の合計を3で割った額がベースになり、現在の標準報酬月額との差が2等級以上あった場合、改定されます。

※保険料額表は、こちらをご覧ください。(資格取得時決定の時と同じ表です)
随時改定の詳細については以下の記事で紹介していますので、参考にしてみてください。
▼計算例
Aさん(46歳・東京都勤務)
現在
- 標準報酬月額:380,000円(健康保険 第26級、厚生年金保険 第23級)
- 健康保険料18,829円・介護保険料3,021円・厚生年金保険料34,770円
4月に大幅な昇給
- 基本給:385,000円
- 通勤手当:20,000円
- 家族手当:15,000円
- 残業手当:4月:10,000円、5月:20,000円、6月:15,000円、
→ 4月:430,000円、5月:440,000円、6月:435,000円
→ 3ヶ月の平均:435,000円(報酬月額)
この場合の社会保険料は、この額を東京都の保険料額表に当てはめると、

標準報酬月額440,000円 (健康保険 第28級、厚生年金保険 第25級)なので、
健康保険料21,802円・介護保険料3,498円(25,300円−20,802円)・厚生年金保険料40,260円となり、この金額が7月から翌年の8月まで適用されます。
産前産後休業終了時改定、育児休業等終了時改定
産前産後休業後や育児休業終了後に報酬が変動した場合、被保険者が事業主を経由して産前産後休業終了時には「産前産後休業終了時報酬月額変更届」を、育児休業等終了時には「育児休業等終了時報酬月額変更届」を届け出ることで、新しい標準報酬月額に改定することができます。社会保険料は復帰月から3ヶ月間の基本給+各種手当の合計を3で割った額がベースになり、現在の標準報酬月額との差が1等級以上あった場合、改定されます。

※保険料額表は、こちらをご覧ください。(資格取得時決定の時と同じ表です)
保険料率・保険料額
ここまで毎月の健康保険・厚生年金保険・介護保険の保険料については、保険料額表から導き出してきましたが、実際の保険料は次の計算式で成り立っています。
保険料=標準報酬月額✕保険料率
- この計算式で算出された保険料を被保険者と事業主が折半して納付します。
- 事業主は別途「子ども・子育て拠出金」を負担します。
| 保険 | 保険料率(東京都例) | 備考 |
|---|
| 健康保険 | 99.1/1,000 | 都道府県によって異なる※ |
| 介護保険 | 15.9/1,000 | 40歳以上対象 |
| 厚生年金保険 | 183/1,000 | 全国一律 |
※各都道府県の健康保険料率はこちら
■保険料額の計算例(東京都、標準報酬月額300,000円の被保険者の場合)

賞与時の健康保険・厚生年金保険・介護保険の保険料はこう決まる!
年3回以内の支給となる賞与の場合、毎月の標準報酬月額の対象とはならず、標準賞与額から健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料が計算されます。標準賞与額は、支給される実際の賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた額をいいます。

※それぞれの保険料率は、保険料額表に記載されているものを使用します。こちらをご覧ください。
※賞与については、実際に支払われた額(標準賞与額)を基に、保険料率を直接乗じて計算します。
よって「保険料額表」にあてはめてはいけません。
※年4回以上賞与が支給される場合は、標準報酬月額の対象となります。
賞与にかかる社会保険の詳細については以下の記事で紹介していますので、参考にしてみてください。
雇用保険料の計算方法
雇用保険料率は、事業の種類ごとに負担割合が設定されています。

一般の事業に勤める労働者の雇用保険料率は
賃金の総額✕5.5/1,000 で計算されます。
▼計算例
Bさん
ある月の給料
- 基本給:300,000円
- 通勤手当:10,000円
- 家族手当:20,000円
- 残業手当:30,000円 の場合は、
(300,000+10,000+20,000+30,000)✕5.5/1,000=1,980
1,980円がその月の雇用保険料となります。
ちなみに事業所は賃金の総額✕9/1,000で計算された額、すまわち
(300,000+10,000+20,000+30,000)✕9/1,000=3,240
3,240円をBさんのために納付します。
労働保険料の計算方法
労働保険料率は、事業の種類ごとに2.5/1,000〜88/1,000の間で設定されています。
労働者の負担はなく、全額事業主の負担となります。

たとえば、「その他の各種事業」の労災保険料は、
賃金の総額✕3/1,000 で計算され、全額事業主負担となります。
最後に
いかがだったでしょうか?
社会保険料は「なんとなく引かれてるもの」ではなく、給与や賞与に基づき、きちんと計算されています。今回紹介した「計算のタイミング」や「計算方法」を知っておけば、
✅ 明細の金額に納得できる
✅ 間違いや過払いにも気づける
✅ 将来の家計管理にも役立つ
社会保険料の理解は、自分の「お金」を守る第一歩です。
ぜひご自身の給与明細を見返して、一つ一つを丁寧にチェックしてみてくださいね。