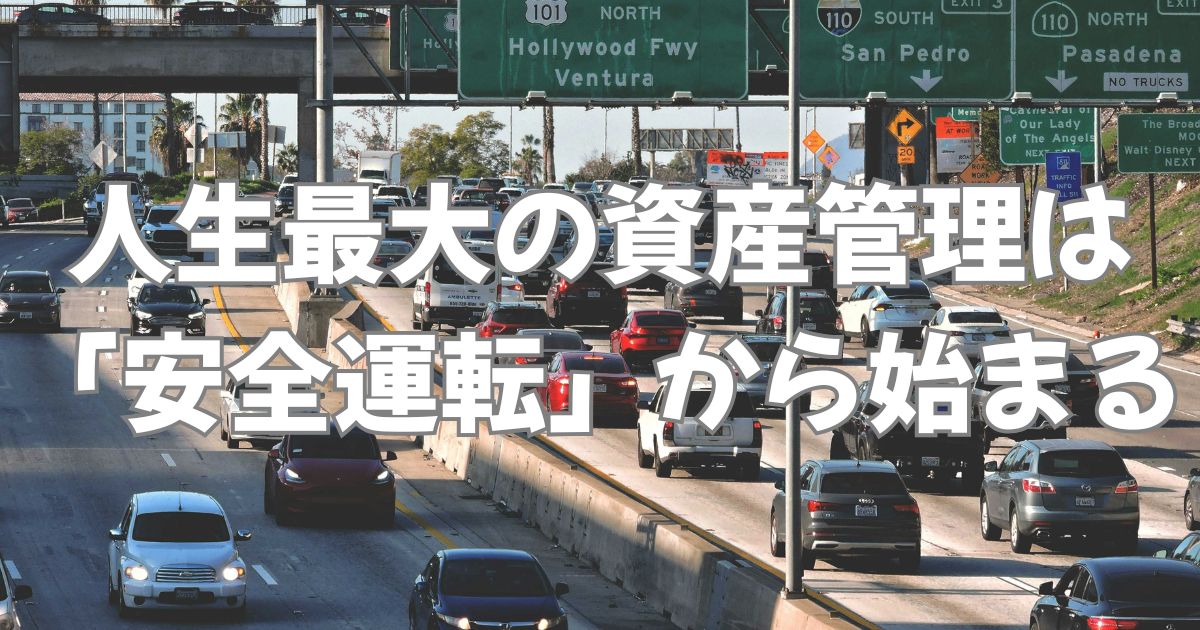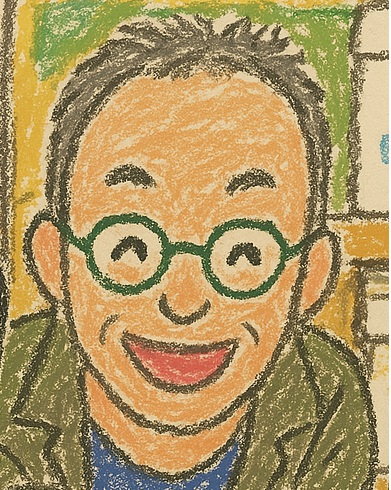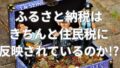日々の運転、つい「慣れ」で運転していませんか?
私は立場上、毎年「安全運転管理者講習」を受けています。
この講習、正直いやいや受けている方も多いのですが、私は毎年新しい発見がある大好きな講習のひとつです。なぜなら、「安全運転=家族や自分の人生を守ること」だと心から感じているからです。
もし万が一、自分が交通事故を起こしてしまったら…。
相手の人生だけでなく、自分の人生、家族の生活、仕事、社会的信用、お金……すべてに大きな影響が出ます。
これはまさに「人生最大の資産リスク」といえるかもしれません。
だからこそ、今この時にこそ「事故を防ぐ=資産管理」という意識を高めておきたい。
今回は、今年の講習で得た学びとともに、「安全運転は資産管理」という視点からお話をしてみたいと思います。
安全運転管理者講習で得た3つの学び
一時停止の本当の意味

一昨年の講習で学んだのは「一時停止」の本当の意味。
単に「止まるだけ」ではありません。
停止線できちんと止まる → その後、左右が見えない場合はゆっくりと車の鼻先を出して確認する。
これを実践することで、左右から突然飛び出してくる自転車などにも対応できるようになり、
何より停止線で止まることで自分の心にも余裕が生まれたのを実感しています。
横断歩道の歩行者優先の本質

昨年の講習で印象的だったのは「横断歩道」について。
鹿児島県は、横断歩道で歩行者に譲る率が全国でも低いという現状があるそうです。
私も
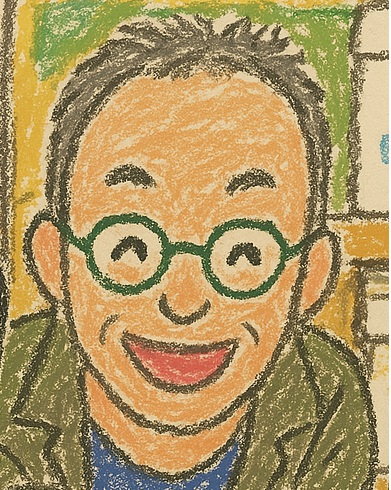
対向車が止まっていないのに、右から歩いてくる人のために止まるの??
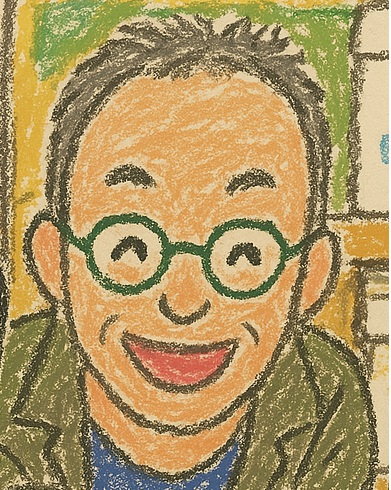
渡るか渡らないかはっきりしないから、こちらは止まらないよ
などと自分に都合よく考えていました。
しかし実は、歩行者が横断歩道に立っている時点で車は止まらなければならないのです。
「渡るか渡らないかわからない時は止まる」、これがルールだと教わりました。
自分の解釈を反省し、それ以来しっかり止まるように心がけています。
「渡りますか?」と確認する
そして今年の講習でも新しい学びがありました。
横断歩道で歩行者が立っていて、なかなか渡らない場合、
「窓を開けて『渡りますか?』と確認する」ことが大切だそうです。
もし「渡りません」と意思確認ができれば、そのまま車を進めてもOK。
これはなかなか実践に移すのは難しいかなと感じましたが、意識するだけでも事故リスクは減らせるはずです。
知っておくべきその他の学び
今回の講習で得た、他にも大切な学びをいくつかご紹介します。
- 狭い道では一時停止がなくても止まる
交差点などで絶対の安全が確認できないときは止まるべき。後続車がいても止まる。 - 路面電車の軌道内では右折待ちはNG
軌道内に入っての右折待ちは禁止されています。
さらに、NotebookLMに今回の講習資料を入れ込んでまとめてもらった重要ポイントは次の7つ:
- シートベルトの完全着用を徹底し、同乗者にも促す
- 高齢運転者の動きに注意し、自身も高齢なら意識的に安全運転を
- 夕方(18〜19時台)の歩行者事故が多いため警戒
- 夜間は「右から左へ横断する歩行者」に特に注意
- 子ども(特に小学1〜3年生)の飛び出しに最大限の注意
- 自転車(高齢者やヘルメット非着用の子ども)との間隔をしっかり取る
- 運転中の携帯電話使用は絶対禁止
資産管理の観点から考える「安全運転」の効果
ここまでお読みいただきありがとうございました。
最後に「資産管理」の観点から、なぜ安全運転が大切なのか、改めて整理してみます。
- 法的トラブル・賠償金などから資産を守る
事故による賠償責任は、場合によっては莫大な金額になることも。 - 事故後の心的ダメージや人生の質の低下を防ぐ
心の健康、生活の質を維持することにもつながります。 - 社会的信用を守る
特に法人代表や経営者にとって、事故による信用失墜は大きな痛手。
そして - 家族の未来(命・健康)を守る
事故がなければ家族との日常が守られます。
こうしたリスクを防ぐ最も身近な方法こそ、「日々の安全運転」なのです。
まとめ 〜「今こそ、安全運転を資産管理の一環に」〜
交通事故を防ぐことは、単なる「交通マナー」の問題ではなく、
自分や家族の「命」「健康」「お金」「時間」「信用」——つまり人生のあらゆる資産を守る行動でもあります。
日々のほんの少しの心がけ、ちょっとした意識の変化が、
大きな事故を未然に防ぎ、未来の幸せを守る力になります。
今は「何もない」からこそ、このことを意識して、
自分自身はもちろん、家族や職場の仲間とも「安全運転」を大切にしていけたらと思います。
私自身もまた、今回の講習で学んだことを実践に活かし、
これからも「無事故・無違反」を続けていきたいと思います。
皆さんもどうぞ、ご安全に!